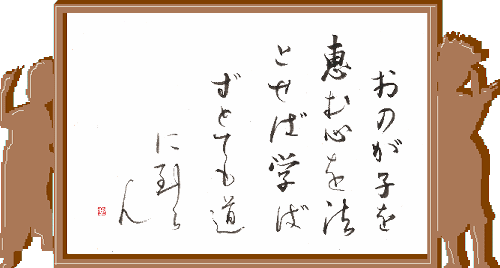書風は「風信帖」を参考にしました。空海(774〜835)が最澄に送った手紙です。まだ平がなの無い時代で、手紙はすべて漢文で、王羲之や当時新しい書風であった顔真卿に似た行草書です。
「弘法も筆の誤り」、「弘法筆を選ばず」といったことわざもあるほど上手で有名です。なお、筆は特製品と思えるものも使っており、選んだと考えられています。指導の初めは筆の持ち方からと教えています。箸を持つように自然に持ち、穂先に少しそりをつけて露鋒、側筆でゆっくり丁寧に書いています。 空海は子供の時から頭が良く家庭教育も行き届き、さらに青年期には記憶力を増す修行もして、日本で学べる限りの仏典を学び、どうしても分からないところを学ぶために31歳の時遣唐使船に乗って留学しました。当時20年が普通の留学期間でしたが2年で目的を達し真言宗の後継者となって帰国しました。
日本初の庶民のための学校であるしゅ芸種智院を創立しました。当時は貴族しか大学教育が受けられず空海の場合、四国出身で入学するのに親戚の力を借り奈良の都に出てから3年かかったのです。学習内容に満足できなくて中途退学しましたが。
国字教育のあり方について考えてみました。 <現状と予測>
毛筆書写技術の習得には時間がかかり、楷書のはね、はらいの筆遣いが困難になっています。 ワープロで書く時代になって、活字に似せた楷書で書く必要はあまりないのではないでしょうか。また楷書の点画を全部書いていたのでは黒板を書き写すのに時間がかかって能率が悪いか乱雑になるかしかありません。これは全教科にかかわる問題です。
日本語は漢字と仮名を混用することによって、表現力と吸収力が豊かな優秀な言語として文化を支えています。反面アルファベットに比べて、文字の習得に時間がかかります。その上、アルファベットと比べて芸術的であり、きれいに分りやすく書きたいと思います。かなも漢字も基本に毛筆があることを理解できてないと書きづらい動きや筆順があります。この点、欧米や中国とは違っています。
西欧では活字体と筆記体を文字の教えはじめから同時に教えています。中国では、てん書・隷書・楷書のどの時代にも補助書体としての行・草書が併用されています。
基本的な筆記体は行草書だと思います。発生的にも行書が楷書より先ですし、日本でトン・スー・トンの3節構造の楷書は小野道風以後では、ここ100年ほど初等教育に用いられただけで、しかも近年の毛筆教育の退化によって、楷書の装飾部分のハネ・ハライが硬筆でも書けない大人が増えてきました。
パソコンで清書するのが普通になった今日、楷書は自分の名前と住所がほぼ書ける程度で良いのではないでしょうか。 楷書が上手になりたい人や漢字文化圏の学習を必要とする人は高等学校や書塾や部活で習うことができます。中世から明治中ごろまで唐様の楷書や行書や隷書は中等教育以上で扱われました。
<筆記体と活字体を両立>
中国政府は簡体字へ改革しましたが現在識字率が上がったということは聞いていません。石井式(石井武漢字教育)では読みと書きは時期をずらして学習するのが自然であり、幼児は仮名より漢字、とくに画数の多い文字を先に識別理解するとしてすぐれた国語教育を実施しています。画数が多くても字義の整った文字の方が分かりやすいのではないでしょうか。たとえば「庁」は「まだれ+耳+王+徳」、「売」は「士+買」、「礼」は「示+豊」、「体」は「骨+豊」、など旧字体の方が意味がわかります。キーボード入力が便利になると文字の画数が少ないことによる利点はほとんどなくなります。
また、楷書で手書きする必要性も激減します。現在国語の時間に楷書の木偏の第2画がハネか止めか、平がなの「れ」の最終画が離れているとまちがいか・・といったことで頭を悩ましているのは無駄ではないでしょうか。「木」を「気」と書いたらまちがい、「れ」は縦棒が左よりになければまちがい、程度の書きとりテストで充分でしょう。
では、その書き取りテストもキー入力で行えばということになりそうです。これは楽しくないと思います。子供が筆記具をもって字が書けたときの嬉しさを思い出してください。「と」の字が左右逆であったり、「す」に点を打って「お」だったりしながら教えてもらって文がつづれるようになり、上手だ下手だと言いながら字を覚えていきます。肉体の運動に音や意味をあわせて全身で覚えるのが早くて楽しい覚え方ではないかと思います。
その時、楷書では楽しさ半減です。平行な線が等間隔に書けない、縦棒が長すぎた、ゆがんだ、払いができない・・・。改めて考えてみてください。楷書は読む人のための書体です。これを読めるように、きれいに、整えて書くことは至難の技です。この困難な仕事を機械がしてくれるようになったのになぜ苦労することがあるでしょう。書くための文字、行草体を学んで手軽にノートを取り手紙を書けばよいのではないでしょうか。
昨年このページの初版にはそこまで書いたのですが、今年「書とは何か」・「WEB公募書展のアンケート考察」を書いた結果、具体的に筆記体のモデルを思い浮かべることができ始めました。
視点は「書とは何か」で書いたように書は視覚表現の芸術であり、音声表現の声楽に対応した言語表現の一方だということです。楷書の線の基本をトン・スー・トンの3節構造とすると、行、草、仮名はトン・スーの2節構造と表現できます。楷書に似つかわしい平がなを書くのに苦労したことを思い出します。現在書道界で調和体・近代詩文の表現を工夫して中央展でも見かけるようになっていますが、本職の書家でも楷書はめったに出していません。筆記体は基本の線をトン・スーの2節のリズムとしましょう。
字形は識別できればよいことにします。言偏は2画・門構えは1画・車偏は4画・木偏は3画・・という風に古典に則って筆記体の標準を決めて教育漢字の行草書体の教科書体を作ります。教科書には明朝体とこの筆記用教科書体を併記します。明朝体を見ながら学ぶので字形に不安が少ない状態で行草書が学べます。読むための明朝体表記、書くための教科書体の漢字は学年相応にします。ノートや黒板に書くのは教科書体です。画数が少ないので速く書けます。かなと調和します。美しい線ができます。装飾的なハネ・ハライがないので誰でも書けます。
音声言語の内、朗読は国語にして唱歌は音楽に含めているのと同様、視覚言語も硬筆は国語、毛筆は美術に含め時間数を増やします。字形やリズムや執筆についても、唱歌が斉唱を教えているように、書も手本通りに書くことを教えます。個性を求めなくてもどうせ個性的にしか書けませんし、大人になったら目的に合わせた書風や師匠を自分で選ぶようになります。
小学校一年生から毛筆で学びます。 書には手先の器用さ、姿勢や呼吸の訓練、集中力の持続、芸術的視点などが含まれています。 筆の感触や運筆の運動性、美的な表現に子供の楽しみがあります。丁寧にリズムをとり、姿勢を確保するためにも縦書きが基本です。
小学校では教科書体を書く、筆順と組み立てを知る、楷書・行書・かな古典の鑑賞。
中学校では楷書・行書・かな古典の臨書、楷書・行書・かな・隷書・篆書の古典の鑑賞と簡単な書道史。
これで実用書先習で、自分の名前ぐらいは楷書で書ける、生涯学習の基礎になる、全教科の学習効率を上げるという目的が達成できます。
<平仮名の字形を変える>
現在の平がなは明治33年の「小学校令施行規則」で字体が標準化されました。それまでは他の草がな(変体仮名)も混用されていたのを一音一字に指定したのです。おそらく、明朝体活字に調和して判読が容易なように選ばれたのではないでしょうか。一般に多く使われていた字や書きやすい字を選んだのではなさそうです。
平がなで書いていてちょっと画数が多く書きにくいと感じるのが「な」「は」「か」「き」・・これらのうちいくつかでも字形を変えたら書きやすくあるいは読みやすくなるのではないでしょうか。
トン・スーのリズムに変えると「し」の終わりが上を向くといった不自然さは無くなるでしょう。明朝体としてはこの形が判読しやすいと思いますが教科書体は変わるとよいと感じます。他の字も柔らかくのびやかな感じになろうかと思います。ついでに「も」は横線を1本にする、「な」は点をなくして2画目の終わりから結びに直接つなぐ。「る」は上を省く、「か」は変体仮名「可」に、「は」は「者」、「き」は「支」、「に」は「耳」か「爾」、「ほ」は「本」、「た」は「多」、「ね」は「年」、「み」は「見」、といった具合に書きやすさを考えて字形を変えることも検討してよいと考えます。この時の字形も活字用には読みやすさ、筆記体用には書き安さを主に決めます。
------------------------------------------------------------
大変な改革のように見えますが、明治の欧化政策と敗戦による米化政策の成果のうち、熟し過ぎた部分をパソコンの普及などの現状に合わせるにすぎません。時代の節目に文字改革のあることは通例です。
------------------------------------------------------------
参考:(日本書道教育学会機関誌「不二」昭和27年2月号・石橋犀水)
昭和27年1月25日に日教組主催の全国教育大会の報告で「国語の読み書きや算数の計算力なども戦前に比べて約2年低下している」ことが明らかにされている。・・・
戦後の習字教育が、展覧会や競書会にあおられて、地味な書写力の陶冶よりも目立つ奇形文字、誤った芸術主義にわざわいされている点も少なくない。・・・
国民の基礎教育においては、もっともっと文字の正確な書写力を養うことが先決でなければならない。終戦後の習字教育がアメリカ教育にならって硬筆習字で間に合わせようとしたのは、・・あまりにも御都合主義で、近視眼的と言わねばならない。・・・
習字教育の今一つの盲点は、小学校初学年におけるかたかな指導の廃止とひらかな優先である。・・かたかな優先は明治・大正・昭和と60〜70年の経験済みである。その形が簡単で直線で構成されているから、複雑な曲線で書かれたひらがなに比して、その習得ははるかに容易である。そればかりでなく、かたかな学習は、漢字学習の基礎として、きわめて好都合にできている。・・・
------------------------------------------------------------
戦後のこの混乱から50年、徐々に改善されて今の状況にあります。残念ながら楷書の基礎、筆遣いの基本ともなるカタカナ優先は果たされませんでした。毛筆を持つのも3年生からです。
時代がかわって見なおさねばならない時がきています。パソコン時代の正確な書写力とは文字の選び間違いをしないということになろうかと思います。それでも、楽しい書生活のために基本のリズムは1年生、カタカナから教えたいものです。 2001.12.18.
主な参考文献 「新講・二宮尊徳夜話」黒岩一郎著 明徳出版社
「くずし字の知識と読みかた」駒井鵞静著 東京美術選書56
石井式教育研究会 WEB SITE
上越教育大学 書写書道研究室 サーバー