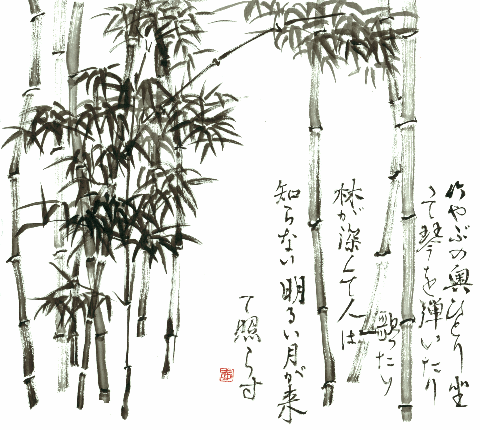臨書には、形を真似る形臨・筆意を真似る意臨・記憶で真似る背臨があります。
このうち意臨とはどうすることなのでしょう。つまり筆意とは何でしょう。元気が良いと思えば元気よく、流れが良ければうまく流す、・・・というようなことでしょうか。しかし、同じ物でも見る人見る時によって感じ方は違います。
二玄社の書道技法講座23唐-顔真卿「争坐位稿」行書-山崎大抱編でこの感じ方を知りました。たとえば- 天=次第次第に筆を吊り上げて、大空に朗々と線を引く。第一、二画は比較的厚みがあって潤い、あとは気の赴くまま心身ともに暢びきっている。
- 定=ウ冠を力強く、下部との間に広い白をとる。百錬の鋼鉄をたわめたような、弾力性に富み、強大な線の迫力は我々を圧倒して止まぬ。
そういわれるとそのようにも見えるので、他の字を私なりに言葉にしてみたら大抱先生とはまるで違います。そこで考えました。形臨でも長さや角度の比率を目測するのはむずかしくて試行錯誤を繰り返すのだから、意臨でも一度に感じ取れなくてよいのではないかと。一画目バシッと見えたらバシッと書いて見る、二画目さらり、三画目ググーッ、四画目のびのび・・・観たとおりに書き上げた結果似てないところは感じ方から改めればよいのではないか・・と考えました。形臨で、だんだん太くとか、このへんで曲げて・・に慣れているせいかもしれませんが、へたな形臨とおなじくらい形も似るのです。しかも面白味があります。芸能人の物まねが服装を似せるより表情やしぐさを似せた方が受けるようなものです。 『竹林に月が出た』ということばは芸術とはいえないでしょう。なにか本質をとらえ、感動し、何らかの方法でそれを表現し、その表現に共鳴する誰かがいてはじめて芸術ですね。『大空に朗々と線を引く』『百錬の鋼鉄をたわめたような弾力』は共感を覚えた私にとって芸術と言えるでしょう。『点画の間を等しく』、『画数の少ない字は小さく肉太に』などの楷書結構法も美しさの要素として学んだときには感動しました。書の鑑賞の言葉はそれ自体芸術と言えるかもしれません。 書道史の上で、臨書の観点が形から離れたのは明の初期の文徴明(1470〜1559)や祝允明あたりからです。明末清初の王鐸(1592〜1652)は一日おきに臨書と自運(創作)を繰り返したそうですが、その臨書はあまり形が似ていません。その臨書作品は自運作品より高く評価されていたそうです。臨書でも本質をとらえた感動があれば、そしてだれか(後世の人であろうと)に伝われば芸術ですよね。書はそっくりに(不可能ですが)書いても盗作ではありません。
★お便りありがとうございました★
書道を学び始めて6年になります。
そろそろ還暦を迎える私にとって書道は
日常生活のストレスから逃れられます。
また最近は書道によるストレスもありますが
生涯の勉強&楽しみと理解してます。
書道の師から学ぶこと、
インターネットでも色々な書の情報がありますが
書の考えを整理するのに役立ちました。
キョンシー